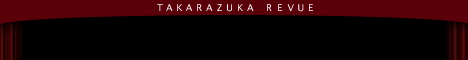難民と演劇 ―― いま演劇にできることとは?
2016年にBrexitを決めたイギリスで、劇作家ジョン・レタラックが2001年に書いた戯曲『ハンナとハンナ』が、再び注目を集めています。
母国コソボの紛争によりイギリスの海辺の町マーゲートに難民として逃れてきた少女ハンナと、マーゲートの低所得者向け高層公営住宅で祖母と暮らすハンナ。16歳の二人の少女が出会い、衝突し、葛藤し、理解し合うまでの過程は、いま世界を揺るがせている避難民とそれを受け入れる国の人々の姿を赤裸々に映しだしています。
2017年7月11日、国際演劇協会日本センターは、世界が直面する現代的課題を解決するための政策研究・教育機関である政策研究大学院大学(GRIPS)とともに『ハンナとハンナ』のリーディング上演を行い、また、難民支援協会の田中志穂さんを迎えて、日本での難民を取り巻く状況を知り、演劇を通して何ができるのかを探るディスカッションを行いました。

◆『ハンナとハンナ』リーディング公演
作:ジョン・レタラック/翻訳:中山夏織/訳詞:田中萌観/演出:鈴木アツト(劇団印象)
出演:木村飛鳥、𠮷岡花絵/アンダースタディ:龍澤幸奈
◆ディスカッション「難民と演劇」
スピーカー:田中志穂(認定NPO法人難民支援協会 広報部コーディネーター)、鈴木アツト
司会:中山夏織(国際演劇協会日本センター理事)
*
● 難民問題とイギリスのEU離脱
中山:鈴木さんは、ちょうど1年ほど前、イギリスがEU離脱を決めた住民投票のときにロンドンに留学中でしたね。
鈴木:2015年11月から翌年9月まで、文化庁の在外研修制度でイギリスに滞在しました。投票は6月でしたが、僕はなんとなくイギリスはBrexitを選ぶのではないかと感じていました。というのは、僕のルームメイトが右翼だったんです(笑)。世間話のなかで、「日本の政権も右傾化しててね」と言ったら、「俺も右翼だよ。難民は問題を起こし過ぎてるから、EU離脱したほうがいいじゃない」と返されたんです。ほんとうに普通のサラリーマンだったので、「これが生のイギリス人の声なのかな」というのが、ロンドンで生活をしていたときの感触でした。
中山:イギリスでも、演劇関係者や大学関係者は「EU離脱なんてありえない」という人がほとんどだったと思いますが、普通の人たちの感覚と離れていたということなんでしょうか。
鈴木:そうだと思います。僕が通っていた英語学校の講師はとても理性的な人でしたが、移民の問題以前に、ブリュッセルのEU政府が物事を決定するということが、システムとして良くないんじゃないかと言っていました。例えば、EUで決められたカカオの含有量に従うと、イギリスのチョコレートがチョコレートとして売れなくなってしまう。そういった生活感覚に根付いた部分への介入、ルールの統一があるんだと知りました。EUはひとつの大きな国のようなものですが、大きくなり過ぎたのかなと思いました。

● 無知ゆえに生まれる受け入れへの不安
中山:田中さんは、この作品をご覧になっていかがでしたか?
田中:事前に台本を読んでいたにもかかわらず、胸に刺さる場面がいろいろとありました。私たち難民支援協会のスタッフが日々葛藤し、向き合っている現実的な問題とまったく一緒だなと思いました。
例えば、見ず知らずの難民の人たちが突然町にたくさんやってきて、知らないがゆえに不安を覚え、その不安が暴力になってしまう、そういう人間の心理ってあるんですね。暴徒化してしまったハンナのお兄さんも、もともと悪いヤツではなく、たぶんすごく不安を抱えていたんだと思います。日本ではおそらく多くの人が難民を見たことがない。それゆえ、日本で受け入れることができるのか心配になったりすると思うのですが、それは難民側の問題ではなく、結局は自分の心の中の問題なんだということを、今日の舞台を見て改めて思いました。

中山:実際の日本の難民受け入れ状況はどうなのでしょう?
田中:日本に逃れてくる人は増えています。昨年は世界の79か国から1万人を超える方々が日本政府に難民申請をしています。ただ、認定された人は28人にとどまっていて、難民認定率は1%にも満たない、宝くじに当たるような確率です。
いまの日本の難民受け入れの問題は、受け入れ数が少ないということはもちろんですが、認定までに3~5年という長い審査期間がかかったり、認められたとしても日本社会に一歩を踏み出す制度的なサポートがないせいで孤立してしまう人が多いということです。
それはなぜなのか。やはり難民を「問題である」ととらえてしまう傾向にあるからだと思います。「どうやったら難民を受け入れられるか」「受け入れられないのは私たち社会の課題なんじゃないか」という視点を持って、受け入れ態勢を整えていくことが進めば、難民もより良いかたちで日本社会へ一歩を踏み出せるんじゃないかなと思います。
● イギリス演劇と難民
中山:私がイギリス演劇の状況を追うなかで、9.11以降、アプライドドラマ、応用演劇の活動で避難民をテーマにしたものが急激に広がっていきましたが、今回のプロジェクトを進める過程で、それ以前のコソボ紛争を境にして避難民たちが対象として大きくクローズアップされてきていたことに気づきました。

鈴木:「アプライドドラマ」について、簡単に説明をしていただけますか?
中山:「アプライドドラマ」あるいは「応用ドラマ」「応用演劇」というのは、必ずしも上演を目的としない、演劇の力、機能を使ったさまざまな活動を意味しています。そのなかには、学校での演劇教育、セラピーなども含まれます。一例をご紹介すると、ルワンダとカメルーンからの二人の避難民の女性がアーティストの力を借りながら、母国での人権侵害、命がけの脱出について語ることによって問題を客観視し、乗り越えていくというプログラムがありました。単に自身の経験を再現するのではなく、映像や照明を使って表象する、違うかたちに変えることで、自分たちを見つめ直すというプログラムです。
調べてみると難民を扱った作品は多くありました。『ハンナとハンナ』の作者、ジョン・レタラックも2002年にグラスゴーでの避難民を扱った『Club Asylum』という作品を書いていますし、2013年にはベンジャミン・ゼファニアという作家が2001年に書いた小説『難民少年』が戯曲化され、上演されています。エチオピアとエリトリア出身の両親を持つ14歳の少年が、どちらの親元にいても殺されるであろうという状況のなかで、親が苦肉の策でイギリスに連れて行き、あえてそこに放置するというストーリーです。
もうひとつ、スコットランドの国立劇場がシチズンズ・シアター・グラスゴーと共同製作した『グラスゴー・ガール』という作品があります。2005年に実際に起きた政府の難民対策への少女たちの抗議運動を描いたミュージカルです。2012年に初演され、昨年エジンバラ・フェスティバルで再演、その前後に国内ツアーも行っています。
● 受け入れる側の視点を描く
鈴木:田中さんは事前に台本を読んでいたけれども、舞台を観て胸に刺さるものがあったとおっしゃいました。俳優の肉声によって伝わることがあったとすれば、我々としては喜ぶべきことなので、詳しく教えていただけますか?

田中:台本は計3回くらい読んだのですが、ここで舞台を観て、ぜんぜん違うなと感じました。目の前で生身の人が演じ、直接思いをぶつける……人が出会うときに抱える不安や、そこで思ってもいない反応をしてしまう葛藤、そういったものがビンビン伝わってきました。
難民をテーマにした本や舞台は、とかく難民側の心境が前面に出ることが多いと思いますが、今回特に印象に残ったのは、イギリス人のハンナの視点、葛藤や苦しみ、もがきが描かれていることです。そこからなりたい自分になろうと成長する姿に、非常に突き刺さるものがありました。
中山:まさに作者のジョン・レタラック自身が「あえてイギリス人側の視点で描いた」と言っています。また、「若い世代は親世代をコピーするのだから、若い世代を変えることからしか始まらない。だから若い人に向けて戯曲を書いた」と話していました。
鈴木:僕が何度も台本を読みながら発見していったのは、脇役がとてもしっかりと描かれているということです。引きこもりだったおばあちゃんが、難民との出会いを通して反ヘイトスピーチデモに参加したり、前向きに変わっていく……そういう描き方も非常に優れているなと思いました。
田中:私もそう思いました。難民に対する反応が人それぞれで、世代でもジェンダーでも区切れない。それぞれが個人として受け止め、変わろうとする。そういった描き方がとても面白く感じました。
● 人間として出会うということ
中山:フロアからもなにかご質問・感想があればと思いますが、いかがでしょうか?
観客A:二人のハンナは一幕目のクライマックスで衝突しますが、分かり合えました。また、二幕目の衝突のあとは喧嘩に終わる。作者は、何があれば分かり合えると書いているのか、また、鈴木さんは何が大事だと考えて演出されたのでしょうか。
鈴木:まず一幕は、「人間として出会う」、そうすれば分かり合えるということだと思います。イギリス人のハンナはコソボ難民を「クズ」と呼んで人間として見ていませんでしたが、不慮の事態が起こって、人間として向き合わざるを得なくなり、そのことが彼女自身を変え、おばあちゃんも変えていく。その「出会い」がきちんと出るように演出しました。
二幕目はハンナがセルビアでの過去を回想するシーンですが、理不尽な暴力はこの世界に現実にあるということ、過去においては分かり合えないことがあったということを、きちんと見つめるというのが主要なテーマなのかなと思います。そのうえで、未来において自分たちはそれをできるだけ回避する、その努力をあきらめないということ。そうとらえて演出していました。

観客B:イギリスのハンナのおばあさんが住んでいるのが公営住宅の11階でした。低所得者が住んでいた「グレンフェル・タワー」(※ロンドンの公営住宅)のこの間(2017年6月14日)の火災とイメージが重なりました。演出上、「場所」についての工夫があったらうかがいたいと思います。また、はじめは流行歌をワーワー歌っているだけだったのが、徐々に歌がひとつの融和のシンボルになっていくのに感動したんですが、今回の舞台で音楽の扱いについてお考えがあればうかがいたいと思います。
鈴木:おばあさんの部屋という場所そのものについては、そんなに意識しませんでした。ただ、イギリス人のハンナにはなぜだかわからないけれどお母さんがいない。お父さんについては触れられてもいない。「少なくとも恵まれた家の子ではないということは必ず押さえておいてほしい」と女優さんには言いました。
歌はイギリスのポップスを使っていますが、訳詞の田中萌観さんと、翻訳の方向性、歌い方など相談しながら進めました。芝居の中で歌を使うとき、同じ歌詞でも芝居の状況によって違った意味に聞こえることがあると思うんです。ただ、日本人のお客さんには英語だとなかなか伝わらないだろうから、思い切った意訳をしています。また、同じ歌でも、どんな歌い方をすれば登場人物の未熟さや成長が表せるかということを念頭に置いて、チームで演出していきました。
● 自分の中のヘイトを見つめる
観客C:田中さんにうかがいたいのですが、いまの日本の社会で難民を受け入れるために必要だと思われることはなんでしょうか。また、このプロダクションを上演することによって、どういう影響を与えることを目標としているか、演出の鈴木さんにうかがいたいと思います。
田中:日本社会になにが必要か……回答があれば私もがんばってやるのですが、なかなか答えが見つからないというのが正直なところです。シリアの内戦が激化し、2011年以降たくさんの方々がヨーロッパに逃れていく中で、日本に入ってくるのはネガティブなニュースが多いですね。そういったニュースを見て、「難民がたくさん来ると大変だから、やっぱり日本は閉鎖しといて良かった」という結論を耳にしがちなのですが、おそらくヨーロッパと日本では、立っているところが全然違うのだと思います。
イギリスもドイツも、すでに多くの移民ルーツの方がいわゆる国民として社会の中核を担う国です。人の繋がりができているので、完全にシャットアウトはしないでしょう。とは言え、「ちょっとしんどい……」といった状況は確かにあるので、ヨーロッパも葛藤しているという気がします。それと比較すると日本はまだ受け入れ能力があると思います。
じゃあ、そういう状況をつくるにはどうしたらいいか。今日は若い人たちがたくさん来ていて驚きましたが、いろいろなところで講演をさせていただくと、中学・高校の生徒さんたちはとても頭が柔らかくて、例えば「日本の政府は難民に厳しいんです」と言うと、「なんでそんなに冷たくするんですか?」「それって国にとってデメリットじゃないですか?」って返ってくるんです。「人を助けることは大切だよね」ということを当たり前にとらえている人たちが、どうやったら自分たちの手でこの難しい問題を解決できるか考える機会がもっと増えれば、少しは変わっていくかなと思っています。

鈴木:単に「ヘイトは悪い」と言っているだけでは、そこで思考停止してしまう。「リベラルの人でも、余裕がなくなると他者を排斥したくなる気持ち、出ちゃうでしょ? そんな自分たちの心を見逃さないで」ということを観客に感じさせたいと思って、ヘイトのシーンでは客席に降りてせりふを言う演出にしました。
「ハンナ」という名前は、コソボ人のハンナが「HANNA」で、イギリス人のハンナは「HANNAH」というスペルです。上から読んでもHANNAH、下から読んでもHANNAH。おそらく作者は、イギリス人のハンナを「鏡」のような存在として描いたんじゃないかと思っています。シェイクスピアの言葉じゃないですが、僕はこの作品を、お客さんが自分たち自身のことを見るように観てほしい、自分自身のこととして作品のメッセージを受け取ってほしいと思います。
二人の名前を続けて書くと「HANNAHANNAH」で、Hを中心にして二人が繋がる感じがします。真ん中の「H」はHumanityだと、僕は勝手に思っていて、人間性を中心に二人が繋がるようなメッセージがみなさんに伝わればなという気持ちで演出しました。

中山:実は、『ハンナとハンナ』には続編があります。15年後のハンナとハンナを描いた『Hannah and Hanna in Dreamland』です。今日見ていただいた『ハンナとハンナ』とその続編をひとつの作品にしたものが、偶然にも明日、ロンドンでリーディング上演されます。二人の女優さんが、14歳のハンナと30歳を過ぎたハンナの両方を演じます。公演が終わったら台本を送ると言われていますので、またみなさんにご紹介する機会があればと思います。
(了)
撮影:石澤知絵子
 iti-japan 国際演劇協会日本センター
iti-japan 国際演劇協会日本センター