今にこそリアリティを持つ『この子たちの夏』
永井 きょうはお忙しいところ『この子たちの夏』をご覧いただきまして、ありがとうございました。いかがでしたでしょうか。
大林 この作品を観て、今にこそ、リアリティがあると思いました。パンフレットを拝読すると、初演が30年前の1985年。一度中断して2011年の東日本大震災の年に再開されたんですね。僕は、2011年は「1945年」に戻ったと思っているんです。僕自身、「1945年以降の日本の復興のやり方は間違いだった。もう一遍、復興をやり直さなければいけない」と切羽詰まっていて、日本の戦争や敗戦後に関する映画を撮ってきました。
さらに、中高校生が「自分たちは戦前世代だ」と言いはじめましたね。高校生が駅前で「私たちの未来は私たちのもの」というビラを配っていたので、「おじいちゃんも一緒に頑張るからね」と言ったら、「おじいちゃんたちに任せているとダメだから、自分たちでやっている。おじいちゃんたちは“戦後”でしょ。私たちは“戦前”です」と高校生にきっぱり言われてしまいました。
子どもたちが、戦争を自分たちのこととして感じているときだけに、彼らに体験者の言葉をしっかりと伝えていくことが、今こそリアリティを持ってきている。この舞台はすばらしいものだと思いました。
下重 今、大林さんがおっしゃったように、3.11というのは、私たちが戦後やってきた間違いを反省すべきときだったんですね。それなのに全く違う方向へ来てしまいました。私自身にとって、70年目というのはもっと静かに迎えるべきものであったはずなんです。ところが、こんなに騒がしい時代になってしまった。若い議員のなかには「戦争に行きたくないというのはエゴだ」という人まで出てきました。
確かに若者たちのなかには目覚めた人もいます。でも、最近の統計では、8月6日は広島へ原爆が投下された日で、8月9日が長崎、8月15日が敗戦の日であると答えられた若者はほとんどいませんでした。これはやはりショックです。戦争の現実をどうやって若者につないでいけばいいのか。『この子たちの夏』もそれをつなぐ一つの催しだろうと思います。
大林 子どもたちは教えられてこなかったんですね。今、子どもたちは本能的に知りたがっています。長崎での平和祈念式典を見ていたら、子どもたちが一番真剣なまなざしをしていた。まるで食いついてくるように「教えて、知りたい、参加したい」という顔をしていました。
下重 今の子どもたちは、歴史の授業で第二次世界大戦を学ばないといいますが、古代からやると、そこまでたどり着かずに明治か大正で終わってしまうからなんですね。でも、考えてみたら私の学生時代ですらそうでした。戦後すぐなのに、授業で出てこなかったのが不思議です。
大林 それはGHQの意向だったんです。占領下の1947年に東京大空襲の慰霊碑を建てる計画があり、GHQにおうかがいを立てたら、「日本人が戦争を覚えている限りアメリカを憎むだろう。そうなると占領政策も米日関係もうまくいかない。ゆえに慰霊碑などつくってはいけない。さらに、子どもたちには戦争なんかなかったことにしなさい」と、GHQはそう答えたんです。つまり、子どもたちに戦争を教えるなという指令がGHQから出ていたわけです。だから日本人は何も知らないまま来てしまったんですね。
戦争を伝えるということの難しさ
下重 戦争が終わった日のことは忘れられませんね。私の父親は陸軍の職業軍人で、母と兄と3人は奈良の旅館の離れに疎開していました。あの日、母が私と兄をラジオの前に座らせ、詔勅を聞きました。そのあと母は「日本は戦争に負けた。軍人の妻や子は強姦されたり乱暴されるかもしれない。そのときは、まずお風呂の中に隠れなさい。それでも見つかったら、これを飲むのよ」と言って、白い粉薬の入った包みを見せられました。後に「あれは何の薬だったの?」と母に聞いたら「青酸カリよ」と言いました。
『この子たちの夏』にも、自分の思いとは違って命を奪われてしまった人たちの話がたくさん出てきましたが、あの敗戦の日は、多くの人が死を意識した、一番大きな節目でしょうね。
大林 私も一遍死んだつもりになっています。私はちょうど原爆投下の1週間前に広島にいました。軍医だった父親を慰問に行って、そのとき路面電車の中から原爆ドームの丸い屋根を見て、これが文明というものかと子ども心に憧れた。
そして1週間後に原爆投下です。私は母親と2人で母親の実家にいました。大家族で、普段は年長の男から、男女別々にお風呂に入るんですが、「きょうはお母ちゃんと一緒にお風呂に入りましょう」と言われて、物心ついてから初めて母親とお風呂に入りました。母はお風呂から出ると長かった髪を切って、私も唯一継ぎの当たっていない緑色のショートパンツと上着のスーツを着せられたんですね。寝間に行くと座布団が2枚、真ん中に短刀が置いてあって、「きょうは二人で朝までお話をしましょう」と言われた。子ども心に、明日、進駐軍が来るから母親は僕を殺して死ぬつもりだと思いましたね。
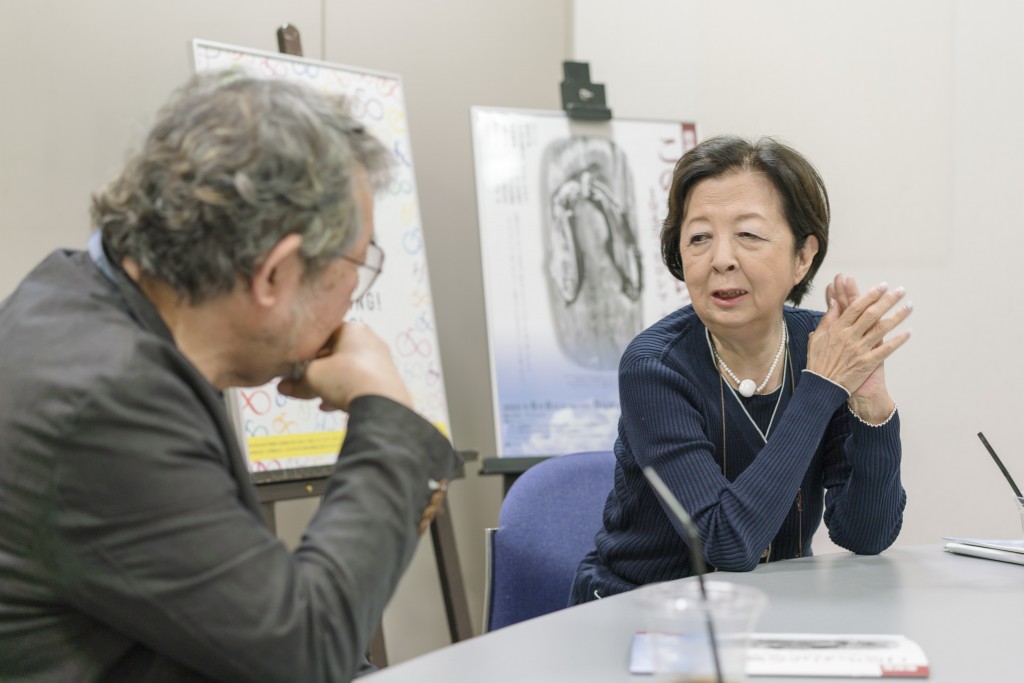
下重 敗戦からしばらくしたら、父親が大きいリュックサックを背負って私たちのいる旅館へ帰ってきました。それから何も言わずに、毎日、毎日、リュックから紙を出して、庭の池のそばで焼いていました。今でも覚えていますが、朱色の罫が入った軍の機密書類です。何日焼いてもなくならない。暑い日で、煙が立ち上って、やたらと赤トンボが多い年でした。そういう風景は、やはり忘れることができませんね。
『この子たちの夏』のせりふにもあるように、その人、一人ひとりの敗戦があり、一人ひとりの原爆がある。「個人」としての戦いをどう受けとめて、どう伝えていけばいいのか、非常に大きな問題ですね。
永井 私はお二人より1~2歳年下で、戦争の記憶があまりありません。
戦後70年が経ち、ジャーナリストの立花隆さんがおっしゃるように、いつか『この方が最後の被爆者です』という日が来る、このままでは忘れ去られてしまうという危機感が私の中にもありました。
あまり知られていませんが、立花さんは学生時代、ロンドンの国際青年核軍縮会議に招かれて被爆地広島の実態を伝えるといったことをされているんです。「被爆の記憶」をどうやって伝えるかを考えた時、そういった“メッセンジャー”のような方が、今後とても大事になると思います。

大林 『この子たちの夏』でも使われている橋のたもとの写真に写っている方で、今まで決して名乗らなかった方がいます。ご主人にも子どもたちにも自分の被爆体験を話していなかったそうですが、やはり後に伝えなきゃいけないと、その方の話から広島県福山の高校生たちがCGで被爆の瞬間を再現したんです。
モノクロの写真を見て「これは何色でしたか?」と聞きながらつくるわけですが、子どもたちが「そこまで聞いていいのか」と躊躇していると、「あのとき100人のうち99人死んだ。今、自分はそれを伝えるために生かされているのだと思うから、どうか全部描いてほしい」と言って、焼けただれた皮膚の色まで細かく再現して作品がつくられました。でも、その方は、「作品ができたのはうれしいけれども、こんなものじゃなかったのよ」と言われるんです。
戦争の実態を伝えるのは本当に難しいことです。1952年、新藤兼人さんが『原爆の子』を広島でつくられた。日本が独立して初めて原爆を取り上げた映画です。それまでは、原爆被曝なんて描けなかったでしょう。敗戦後、広島に「よく効く頭痛薬ピカドン」というものがありました。要するに、原爆の恐ろしさが教えられていないので、むしろ原爆の「威力」に憧れていたんです。
下重 恐ろしい話ですね。
大林 新藤さんの作品はリアリズムなので、ピカとドンのときに、全裸の少女がその光と爆風にあおられて死ぬところを描きたいと言われた。そうしたら広島の女学校の校長先生が「うちの学生を出します」と言われて、実際に女学生が演じました。『原爆の子』はカンヌに出品されたのですが、日本の外務省はカンヌに受付拒否してくれと依頼しているんです。つまり、敗戦国がみずから被爆による被害を発信するのは戦勝国の対日感情を刺激するということへの“配慮”ですが、カンヌは受けつけてくれました。
その後、日教組プロの関川秀雄さんが『ひろしま』をつくりました。これもリアルなピカドンの姿を再現しようと、広島の老若男女が8万人ほど出演して、一つの画面に2万人ぐらい出ているんです。だけど、広島の人は皆、「こんなものじゃないよ、ピカドンは」と言うんですね。つまり、どんなにリアルにやっても描けないんです。
想像すること、感じること
永井 一方で、実際に広島で原爆を受けた方たちの中には、それを言うことに対する拒否反応もありますね。
大林 末代まで嫁に行けないとか、謂れのない差別や偏見がありますからね。『この子たちの夏』の最後に、「私は誰にも文句を言おうと思いません。よくなろう、生きよう、生きぬこう」という言葉があります。この勇気は、差別に対する決意なんです。つまり、「自分は原爆に遭ったことを全部認めて、それを言います。そうやって生きていきます」という宣言なんです。
下重 原爆を受けていかに悲惨な目に遭ったかというのが第一段階だとすると、その後、生きていく覚悟をしなければならないというのが次の段階ですね。私は、『この子たちの夏』の第3部に出てくる「長崎の平和の像を立てたお金、あのお金があったら何ができただろう、『平和』という言葉が空しい」という台詞が一番耳に残りましたね。本当にリアリティがある。私たちはなにげなく「平和」という言葉を使うけれど、一体何をしていて、何をしてきただろうという、その空しさが込められていますよね。
大林 平和というものは戦争の対義語としてあるわけで、本来は「戦争を忘れてくれるな」ということなんですよね。つまり、痛みのない平和というのはないんです。痛みも敗戦も知らずに「平和だ、平和だ」と言っているのは、「平和難民」でしかない。
下重 「70年間、平和であった」という言い方は、70年間、危機感すら持ってこなかった、そういった想像力も持ってこなかったということではないかという気がします。
大林 その想像力というのが実は一番大事で、映画もどうやったってリアルにはならないんですよ。じゃあ、どうすればいいかというと、想像力なんです。
例えば、高畑勲さんがアニメーションの『火垂るの墓』といういい映画をつくったんですが、御当人にうかがったら、戦争体験者からは、「高畑さん、絵が違う。あんなもんじゃなかった」と叱られると言うんです。あれはセルアニメという手法ですが、高畑さんは本当は紙芝居の絵でやりたかったそうです。紙芝居の絵というのは稚拙だけれども「記憶」だから。リアルなものは「記録」であって、「記録」に立ち向かっても、劇映画では決して再現はできない。だけど「記憶」だと再現力があるんです。被爆者が描いた絵も、稚拙だけれどリアリティがあって、力があるんですね。それで僕も『この空の花―長岡花火物語』では全部、紙芝居の絵にしました。まだ技量が定まっていない長岡造形大学の学生さんたちにしっかりと事実を学んでもらって、彼らの想像力で描いてもらったんです。
永井 「素人の持っている技術」というか、リアリティというのはすごく大きいものがありますね。
大林 一見難しい映画のように見えるでしょう。でも、4歳の子どもが一番いい観客でした。2時間40分もの映画を見終わって、「お父さん、僕、今、生きているの?」と聞いたと言うんです。
下重 すごいですね。
大林 生きているなんていうことを考える年齢じゃない子どもがそう言ったので、お父さんが、「生きているだろ。だから、お父さんとこうしてきょう映画を見てお話ししているだろ」と言ったら、「じゃあ、あの一輪車のお姉ちゃんは生きているの?」と聞いたんです。これは、過去に戦争で死んだ子どもが一輪車に乗っているシーンのところを言ってるんですね。
それでお父さんが、「君があのお姉ちゃんのことをいつまでも忘れないで大好きでいたら、君が生きているのと同じようにお姉ちゃんも生きているんだよ」と言ったら、4歳の子どもが、「うん、わかった。僕はいつまでもあのお姉ちゃんのことを大好きだから、ずっと一緒に生きていけるね」と言ったんです。これで、この映画で言いたかったことは全部伝わっているんですよ。理解はしなくても、感じてくれているんです。

下重 そう。感じることですよね。
大林 感じてくれれば、わかってくれるんですよ。
永井 感性の共有ですよね。
下重 私は人間って意外と進歩しないと思っていて、私自身も、方法論はいろいろ変わっても、考えていることや感性は、小さなころと何も変わっていないんですね。だからこそ、小学校時代にそういうものを見なければいけないという気がします。
大林 『この子たちの夏』も、子どもが観れば大人以上に感じてくれると思いますね。
永井 ぜひもっと若い人たちに見てもらいたいと思っているんです。
下重 学校からは観に来たりはしないんですか。
永井 観に来てくださっていますね。中学生のお子さんを同伴された場合の親子料金も設定しています。演出・構成の木村光一さんが音声も照明プランも全部使っていいという許可をくださっていて、過去にアマチュアの方による公演が行われたこともありますし、今回の公演も短歌の部分だけは、世田谷区の中高生に読んでもらっています。
私は「子ども向け」につくったものはあまり好きじゃなくて、大人が観てもいいもの、最高のものを見せたい。それを子どもが見て、感じるものがあると思っているんです。
大林 本来「大人だまし」っていうのはありますが、「子どもだまし」っていうのは本当はないですからね。子どもは決してだまされませんから。
下重 見せるだけじゃなく、子どもたちにやってもらったらどうですか。私はやるほうが伝わると思います。自分に残るでしょう。子どもたちがこれを自分で読めば、自分が体験したかのような気持ちを持つことができると思いますね。
一人ひとりの思いを引き継ぐ歴史教育を
大林 去年、日本非核宣言自治体協議会に呼ばれて藤沢で「ピース・フロム・藤沢」という講演会をしたとき、僕が出番を待っていたら中学生が二人血相を変えてやって来て、「監督さん、僕は将来政治家に、こいつは経済家になろうと思っているんです。政治も経済も夢じゃないでしょう。現実でしょう。だから、現実のアメリカやイギリスや中国や、日本と戦争をした人たちが原子爆弾についてどう思っているかを僕たちに教えてください」と、目を輝かせて言うんです。
僕は子どもたちにアメリカで1952年につくられた『原爆下のアメリカ』という映画の話をしました。1,000発の原子爆弾を積んだ1,000機の軍用機がニューヨークを攻撃するんですが、ガラガラと壊れるだけでピカもドンもない。つまり、核被害が描かれていない。この映画は「原子爆弾には核被害がない」ということをアメリカ国民に教える映画だったんです。「広島、長崎の原爆のおかげで日本は平和になった」と。
下重 実際にそう信じられていますね。昔、私が英語を習っていたアメリカ人女性で、「原爆の子の像」のモデルの禎子の映画『千羽鶴』の上映会をアメリカ各地でやっている、いわば反戦の士のような人がいたんですが、彼女と原爆の話をしていたら「パールハーバーがあったから原爆があった」と原爆投下を正当化していました。すごくショックを受けましたね。
永井 でも、アメリカでも原爆投下に関係した人たちの精神的苦悩が伝えられたりして、「原爆を落とさなければ戦争は終わらなかった」という説がだんだん変わってきているようですね。
下重 少しずつですね。中国の場合は、盧溝橋のすぐそばなどいろいろなところに立派な戦跡の記念館があって、日本の残虐さなどが子どもたちにも伝えられています。そうやって見せて教育されていくわけですから、日本とは全然違ってくるわけですね。
大林 よくも悪くも国の事情だけれど、中国も韓国も教えられている。日本だけが教えられていない。日本の子どもたちは、太平洋戦争で中国やソ連と戦争をして負けたということを知りませんからね。
下重 日本の場合は、何年何月に広島に原爆が落ちたという事実と日にちに重きが置かれている気がしますが、そういう教え方に問題があるのだと思います。事実はもちろん大事ですが、そのとき生きていた人たちの思いを引き継ぐこと、私はそれこそが歴史教育だと思うんです。いま、思いを引き継ぐということを全然教えていない、思いが伝わっていないんです。
『この子たちの夏』を観て、こういう思いを引き継ぐ歴史の伝え方が、もっと教育の現場であっていいと思いましたね。
大林 特に高度経済成長期のころから、情報時代になったでしょう。情報というのは「各論」であって、各論は「是か非か」になっちゃうんですね。
永井 今、ネット時代で、ニュースがそうなってしまいましたね。
大林 だけど大事なのは各論じゃなくて総論で語ることです。総論で語るということは、過去から学んで、未来を想像して、今をどうするか。つまり総論の中には「私」が出てくるわけです。総論は「正気」で、各論は「正義」なんです。正義というのはそれぞれの都合です。日本の正義とアメリカの正義が戦争をして、勝ったアメリカの正義が正しかったというのが戦争でしょ。正義は、結局、戦争を生むんです。正気でいるということは総論で考えること、下重さんのおっしゃる想像力であったり、そこにいた人たちの気持ちを考えるということですね。
永井 次の戦争はもう破壊ですからね。
下重 原爆が落ちたとき、戦争に負けたとき、そこにいた人たちがどんな気持ちでいたかを一人一人が語られています。国や団体じゃなく、個人がどう受け止めたか、それを伝えていかなければならないと思うんです。
加害と被害、双方の祈りを花火に込めて
大林 私が長岡にほれ込んで『この空の花』をつくったのは、花火を見に行ったのがきっかけでした。毎年8月1日の夜10時30分に上がるんですが、それがちょうど爆撃のあった時間なんですね。
下重 私は『鋼の女』という本で、長岡瞽女の小林ハルという人間国宝になった人の話を聞き書きしたんですが、長岡の一番ショッキングな場面が、空襲で焼けた日のことでした。彼女たちは目が見えなくても、ちゃんとわかる。気配と音でわかるんですね。
大林 長岡のお年寄りは花火が始まると家にこもって、花火を見ないそうです。
下重 わかりますね、そのお気持ちは。
大林 それでも、爆撃のことは伝えなければいけないというので語り部となって子どもたちに伝えている。しかも長岡は真珠湾攻撃を指揮した山本五十六の郷里なんですね。長岡市長さんが「いつか僕はパールハーバーでこの花火を上げたいんです。五十六の里の政治家だからやるべきことはやります。覚悟は決まっています」と言われて、それで僕も、「じゃあ、私は映画をつくるから、パールハーバーで一緒にやりましょう」と約束したんです。その花火が、今年の8月15日に上がるんです。
下重 本当ですか! パールハーバーに長岡の花火が上がるんですか。
大林 長岡の戦災資料館では、真珠湾にある戦争資料館「アリゾナ記念館」と組んで日本の加害も訴えています。戦争というのは被害だけじゃなくて、みずから加害者になることが恐ろしい、そういう教育をきちんとしているんですね。そんな交流があって、2012年にホノルル市と姉妹都市を締結したとき、そのときはパールハーバーじゃ無理でしたが、ホノルルの海辺で花火を上げて映画もやりました。怖かったですね。上映の日の朝、ピストルがずっとこっちを向いている夢にうなされて、会場に行ったら異様な雰囲気でした。市長さんも横で震えていました。私も震えています。
終わったら私と同じ年ぐらいの白人女性が一人、血相を変えてやってきました。目をつぶるとナイフを持っていたように思うんだけれども、そんなことはなくて、僕の手を握り締め、振り回して「映画を見ている間中、私の胸は嵐のように騒いでいた。でも、映画を見終わった今、あなたはこれから未来を生きるアメリカと日本の若い人のためによいプレゼントをしてくれたのではないかと思う。だから、私はそれを信じます。Thank you very much. わかりますか? 私のこのThank you very muchは、私の勇気です」と、そう彼女は言ってくれました。
長岡の花火というのは、シベリア抑留された人が上げていて、ゆっくり開いてゆっくり散る、いい花火なんです。
下重 私も見たことがあります。一番大きい三尺玉、あの花火はすばらしいですね。
大林 その花火がようやく今年、パールハーバーで上がります。こういうことで伝えることもやっぱり必要だし、『この子たちの夏』も、あの日の一人ひとりの声を子どもたちに伝えられればいいと思いますね。
永井 今、広島に行くと本当にきれいになっていて、あそこに本当に原爆が落ちたのかしらと思ってしまいますね。
大林 暑さだけは同じでした。「ああ、あのときもこんな暑さだったな」ということは残ります。だから、客観性じゃだめなんです。普遍性で伝えるということが大事だし、そういう意味で『この子たちの夏』のような活動はもっとも大事なことだと思いますね。

(2015年8月9日・公益財団法人せたがや文化財団会議室にて)
構成・文/中島香菜
撮影/山田泰士
 iti-japan 国際演劇協会日本センター
iti-japan 国際演劇協会日本センター




